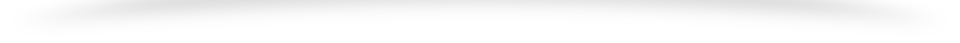社内報ご担当者様から「自分の原稿がもっとよく書けたらなあ…」というお悩みの声をよくいただいております。
原稿こそ社内報の命。記事の目的に沿った、読み応えのある記事になってこそ、読者へ思いが伝わる社内報になります。
今回は社内報の特徴を踏まえて、原稿をブラッシュアップしていく観点を見ていきましょう!
(1)分量に合った原稿になっているか?
指定字数をオーバーしてしまう要因のひとつとして「伝えたいこと」の優先順位が明確化されないまま書かれていることが挙げられます。
文字数がオーバーした場合は、重要性の低い箇所(それがなくても趣旨が伝わる箇所)を削除していくことで、より伝わりやすい文面にすることができます。出来事の経緯を丁寧に説明する箇所などは、分量が厳しい場合は優先的に削除できるでしょう。また、まとまった箇所を削除することが難しければ、全体に「例えの表現を減らす」「繰り返し出てくる言葉をひとつにする」「同じ意味で文字数の少ない言葉に置き換える」などの処理を施してみましょう。
(2)原稿のスタイルは「伝えたいこと」に合っているか?
例えば、新任者の自己紹介記事の場合。出身地や経歴、プライベートな話題や今後への抱負などをひとまとまりの文章にすると、時として冗長に感じることがあります。
その場合、思い切って、一問一答のスタイルにまとめなおしたり、インタビュー形式に仕立てたりするとよいでしょう。
質問と回答に文章を切り分けることで、見た目にも読みやすくなり、読者にも新任者の人となりが伝わりやすくなります。社員の紹介記事では、その人の人物像をはっきり伝えられれば、必ずしもまとまった文章に仕上げる必要はないのです。
どことなく原稿が腑に落ちないときは、原稿のスタイルという根本的な部分から再考するのも解決策となり得ます。
(3)記事の方向性に合った表現になっているか? 【ニュース記事編】

社内報に掲載される記事には、いくつかの種類があります。それらの種類に合った原稿に仕上げることが重要です。
まず、社内報で多くの割合を占める「ニュース系記事」。イベント実施の報告や、研修開催のお知らせについて伝えるような記事では「正確な事実」と「『なぜ』それが行われたか」を伝えることが重要です。
文章の冒頭では、ニュースとして扱う出来事の5W(いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ)が伝わるよう配慮し、簡潔かつ正確に報告しましょう。その上で、もっとも力を入れたいのは「なぜ(WHY)」の部分です。
例えば「なぜグループ社同士の交流会を行ったのか?」という問いに対しては「社員同士の結束を深め、ともに発展していくきっかけとするため」。
「なぜハラスメントの研修を実施するのか?」という問いに対しては「従業員の不安を取り除いて安心して勤務してもらい、より高いパフォーマンスを実現してもらうため」。
このように、会社が起こすひとつひとつのアクションに込められた思いを伝えることは、結果的に社員間でのビジョンの共有につながっていきます。
(4)記事の方向性に合った表現になっているか? 【対談・座談会系記事編】
「対談・座談会系記事」では、印象的だった部分に着目することで、読み応えのある記事に仕上がります。
ポイントは、実際の会話の流れの順番を死守する必要はないということ。たとえば、会の冒頭で「今後に向けた展望」の素晴らしいコメントが取れたとして、それは記事の冒頭よりも終盤に掲載する方が生きてくるはずです。
正確な対談内容の再現に拘泥してしまうと、かえって参加者の最も言いたかったことが伝わりづらくなりかねません。実際の会話で話題があちらこちらに移っていた場合は、話の流れを一つに絞るなど、記事内で要素を動かしながら調整した方が記事としては読みやすくなります。
また、正確で堅い文章ではなく、臨場感を損ねないように「そうですね」という相槌や、「えー(笑)!」といった間投詞など、口語的な表現も生かしながら、参加者の重要な発言をもとに構成していきましょう。
**********
この他にも、以下のような基本的な文章の約束事を守ることが重要です。
・一文一義で執筆する
・主語・述語のねじれを整える
・文体を常体(~だ・である)か敬体(~です・ます)のどちらかに揃える
自分でも納得できる文章を掲載し、自信を持って社員の皆様に社内報を配布しましょう!
【関連記事】
何を書いたら良いのか分からない人、必見! 原稿執筆・寄稿文のヒント

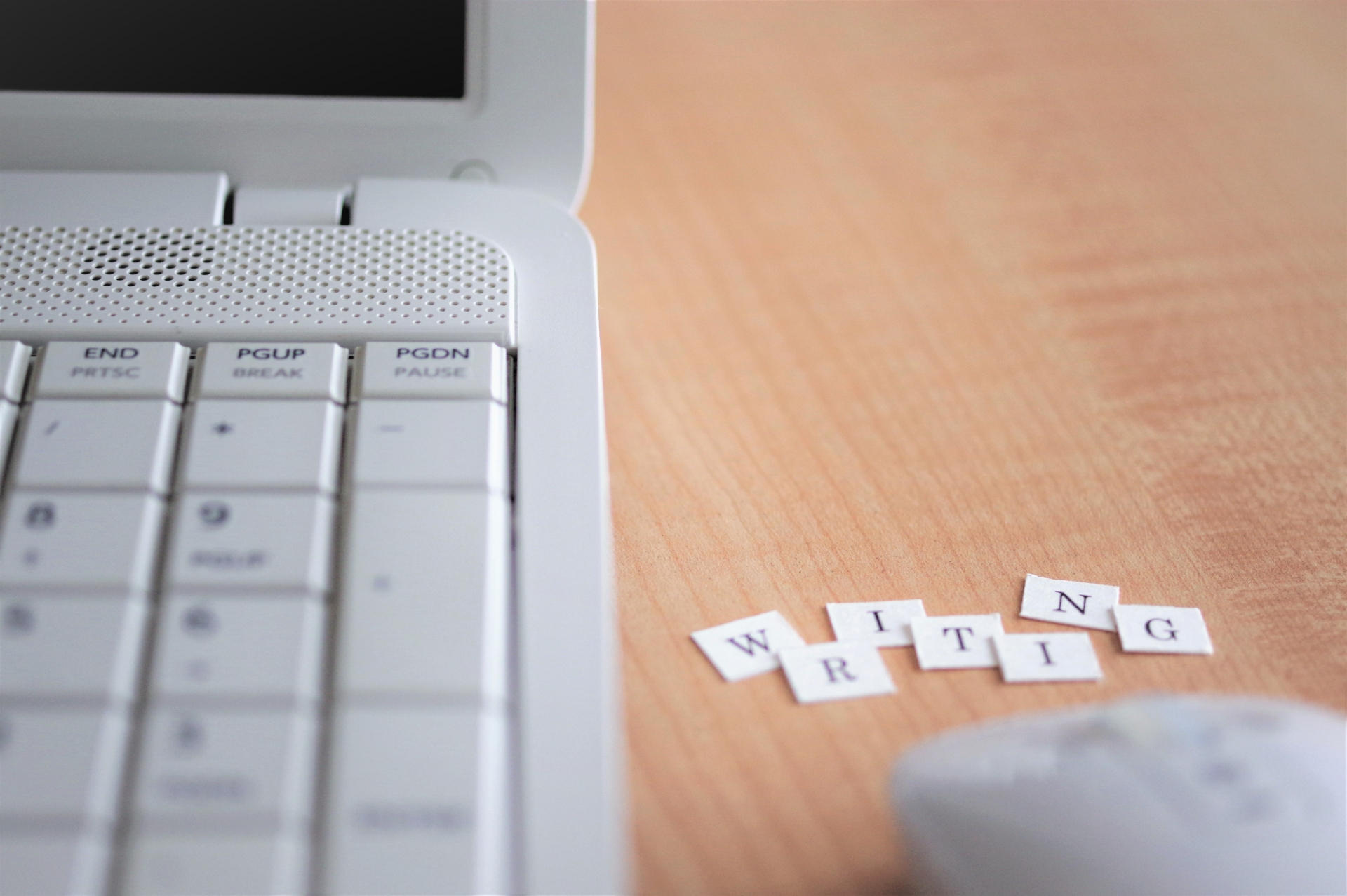
 ディレクター:今枝
ディレクター:今枝