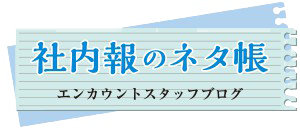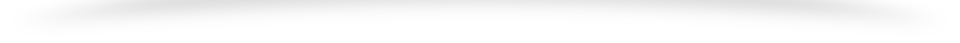社員インタビューや座談会など、社内報には文字量の多いコンテンツがよく掲載されます。ボリュームのある文章を最後まで読んでもらうためには、重複している表現を削除したり、遠回しな表現をわかりやすくしたりと、原稿を整理してできる限り読みやすくすることが重要です。
それでも本文の文字量が多すぎると「見た目の圧迫感」がなかなか消えないことはありませんか?
そんなときは、原稿を「本文」と「本文以外の要素」に分ける、という編集テクニックを使うのがオススメ。執筆者に許可を得た上で本文を減らし、本文以外の要素に振り分けることで、誌面にメリハリを生むことができます。今回は社員インタビューを例に、3種類のテクニックを紹介します。
テクニック1:脱線トークは「エピソード」として本文の外に逃がす
本文の中で本筋から脱線している部分やこぼれ話的な部分があり、そこで分量がかさんでいる場合は本文から外し「エピソード」「こぼれ話」などと小見出しを付けて、コラムとして読ませるというテクニックがあります。本文がスッキリする上に「箸休めコーナーがある」という印象を与えるので「長い文章を読みたくない」という読者のストレスを低減することにもつながります。
(例)
〇〇さん:大学時代はラグビー部に所属していました。最後の試合は接戦の末に敗れてしまったのですが、仲間たちと4年間一生懸命練習した経験は、業務に取り組む姿勢にもつながっていると思います。ちなみに、今日つけているネクタイは、卒業時にラグビー部の後輩からプレゼントされたものなんです。サプライズだったので本当にびっくりしたのですが、自分のために準備してくれたのがうれしくて、つい泣いてしまいました。
↓
〇〇さん:大学時代はラグビー部に所属していました。最後の試合は接戦の末に敗れてしまったのですが、仲間たちと4年間一生懸命練習した経験は、業務に取り組む姿勢にもつながっていると思います。
…(中略)…
【インタビューこぼれ話】
〇〇さんが当日バッチリ締めていたネクタイは、ラグビー部の後輩から卒業の際にプレゼントされたというお気に入りのネクタイ! もらった際は、うれしくてつい泣いてしまったそう(笑)。
テクニック2:社員の経歴や数字に関する情報は、表にしてスッキリさせる
たとえばインタビューの冒頭、自己紹介として経歴を語るパートがある場合は「年表」にするという手段があります。本文に書くよりも端的に伝えることができ、誌面の見た目もスッキリします。
また、過去の実績などを数字ベースで紹介するパートも、文章では読みながら頭の中で整理するのが難しいことも。そんなときも「20XX 年 売り上げ〇〇〇円達成」「20XX年 新規受注〇〇〇件達成」など、年表にすると実績がわかりやすくなります。
(例)
20XX年に中途で入社したと同時に、〇〇〇社に出向し、新プロジェクトに携わっていました。 そこで5年ほど研究開発を担当し、本社へ戻って新しいチームのリーダーになりました。
↓
20XX 中途入社
〇〇〇社で新プロジェクトの研究開発に従事(出向)
20XX 本社にて新チームのリーダーに
テクニック3:長くなりがちな「言葉の意味の説明」は注釈にする
社員インタビューのような口語調を生かした原稿では、言葉やものの定義について解説する文章が冗長になります。注釈として文章の最後やページ下部などにまとめて書けば、本文の流れをスムーズに保つことができます。ただし、注釈だらけの文章はかえって難解な印象を与えて読みにくくなることもあるため、使うのは重要な箇所に絞りましょう。
(例)
現在は研究員として、インターネットの〇〇〇分野に関する研究を行っています。〇〇〇分野に関する研究というのは、要するにコンピューターをより快適かつ便利に利用するための取り組みなのですが、なかでも、ユーザーにとってのサイトの利用しやすさに関する研究が中心です。 …
↓
現在は研究員として、インターネットの〇〇〇分野に関する研究※を行っています。…
※コンピューターをより快適かつ便利に利用するための取り組み。特に、サイトの利用しやすさに関する研究が中心。
原稿は、必ずしもすべての内容を「本文」に入れ込む必要はありません。一部を「本文ではない要素」にまとめ直すことは、見た目の圧迫感を低減させ、読みやすさを向上させるための編集テクニックです。本文の流れを意識しながら、分かりやすく読みやすい構成を目指していきましょう!
〈関連記事〉
“あ〜どうしよう!” 原稿量が多いときの秘策
この原稿、いい原稿…? 迷った時のチェックポイント